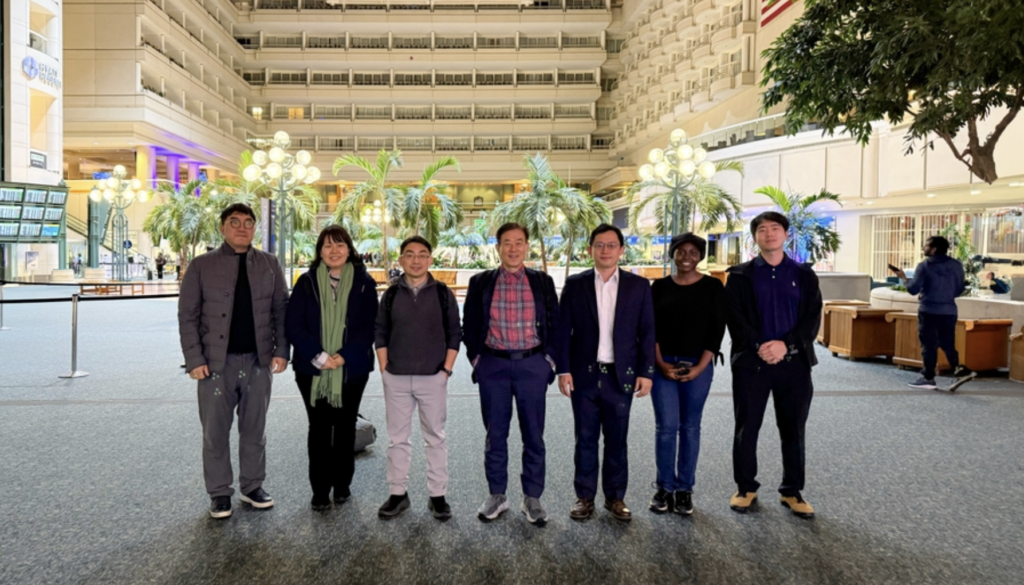1. 福音と愛
福音とは、キリストの愛の物語です。教会が伝える「良い知らせ」であり、イエス・キリストの生涯と教えを通して私たちに示された、神の救いのメッセージでもあります。この福音がなぜ「愛」と結びつかざるを得ないのか、またなぜ福音が犠牲的な愛の極みを示すのかは、聖書の多くの箇所で確認できます。聖書学者たちが「最もよく福音を説明した章」と呼ぶルカの福音書15章には、救いと愛の核心が込められています。同時に、福音の本質は人生の変化であり、その変化は最終的に「人間が神のかたち(イマゴ・デイ)を回復し、人間本来の姿になる道」であると言うことができます。ところが、この福音が単なる人間の感情や一時的な熱狂にとどまらず、実際の生活の中で具現化される「愛」となるためには、その源が神にあり、その実践的内容は「犠牲」として表れなければなりません。
多くの人々は、福音を教会が伝えるある種の教理や信仰体系だと考えることがあります。しかし、イエス様ご自身が生き方で示された福音は、文字通り「一人のいのちのために自分のすべてを捧げる愛」にほかなりません。その愛の本質を分析的に描写した代表的な章が、コリント人への第一の手紙13章です。都会の言葉で表現したパウロの「愛の章(章節)」は、愛の属性を非常に論理的かつ解説的に解き明かしています。「愛は寛容であり、愛は親切です。また、人をねたみません…」と始まるみことば(第一コリント13:4以下)は、世界のどこで聞いても理解しやすい普遍的な言葉です。しかし、これがただの道徳的教訓でも礼儀作法としての愛でもなく、「キリストが十字架で示された犠牲的愛」であることを悟ることが重要です。
第一コリント13章の最後の部分で、パウロは「主が私を知っておられるように、私も全く知るようになる」(第一コリント13:12)と述べ、愛を「知ること」と同一視しています。ヘブライ語で「知る」という語は、単なる知識習得ではなく、人格的な交わりと深い親密さを意味します。それほど愛には、互いを深く理解し受け入れる関係的側面があるのです。ここで「主が私を知っておられるように、私も全く知るようになる」というみことばは、言い換えれば「主が私を愛してくださったように、私も完全な愛をもって主を知るようになるだろう」という意味にも解釈できます。このように、愛の本質は神との親密な交わりに根ざしています。
ヨハネの手紙第一4章19節で「私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです」と教えるように、福音は神が先に私たちを愛されたという宣言です。私たちが「愛を学ぶ」と言えるのは、まず神から愛されたからであり、その愛に気づき深く味わっていく過程の中で、私たちも他者を愛する存在へと変えられていくのです。このように、福音は徹底的に神の愛と犠牲から始まります。そしてその対象はすべての人々、さらには徴税人や娼婦にまで及びます。イエス様は死に至るまでご自身を低くされ、そのへりくだりと犠牲のうちに神の愛が最も明確に示されました。
ローマ人への手紙10章では、「人は心で信じて義とされ、口で告白して救いに至る」と語られています。信仰とは、まず心が開かれ、そこから自然に告白へと至るものです。しかし、その心が開かれるきっかけはさまざまです。先に知的理解を得てから心が開かれる場合もあれば、先に心が開かれて後から知的理解が続くこともあります。重要なのは、最終的に心と理性の両方が共に動いてこそ、完全な信仰と愛の実践が可能になるという点です。ギリシア人が「人間とは理性を持つ存在だ」と強調したように、私たちが「愛とは何か」「主がなぜ私たちを救われたのか」「なぜ私たちは主を信じるべきなのか」を熟考することは非常に重要です。この悟りがなければ、私たちの信仰が形だけに陥ったり、慣習的な行為に堕する危険があるからです。
では、愛とは具体的に何でしょうか。聖書が一貫して語る愛は「犠牲」です。歴史的な例としてよく取り上げられるのが、ポンペイ(Pompeii)の火山爆発で街が埋もれた時、母親が子どもを抱きかかえたまま亡くなった痕跡が発見されたという話です。噴火から子どもを守るため、自分の体で覆って救おうとした母親の本能的な犠牲が、そのまま化石のように固まって残っていたのです。これはいのちを守ろうとする愛がどれほど強力な力を持つかをよく示しています。一般的に、生物の本能は自己保存に傾く傾向があります。植物も地中から芽を出す時、互いに譲り合うよりも自分がより多くの光や栄養を得ようと競争します。しかし愛は、この自然的本能とは異なり、「自らを犠牲にしてでも、他のいのちに道を開き、守る」行動を可能にします。
私たちは、イエス・キリストが示された生き方、すなわち十字架上での死こそが「犠牲的愛」の頂点であると告白します。イエス様の十字架の出来事は、罪のない清い方が罪人の救いのために代わりに死なれた、最も劇的な愛の行為でした。張ダビデ牧師が度々説教や講演で強調するように、福音の核心はまさにこの犠牲にあります。主の死は、単に宗教的象徴や儀式ではなく、私たち全員に向けて「このようにしてあなたがたを愛しているのだ」と直接示された、行為による表明なのです。世にはさまざまな愛の形がありますが、「自分のすべてを惜しみなく捧げる愛」は最も究極的な形であり、それこそがキリスト教の福音が伝えるメッセージの本質でもあります。
さらに、私たちがこの愛の価値を悟るなら、その犠牲が決して無駄ではなかったことに気づくはずです。「犠牲」という言葉を漢字で「犧牲」と書く時、「牛」を意味する文字が含まれているとよく言われます。牛は一生、畑を耕し、力を尽くして主人を助け、最後には肉も革も骨も、さらには尻尾までも捧げ、人間に貢献します。牛が生涯をかけて主人に仕えるように、イエス様はご自身の生涯すべてを私たちのために捧げ、その愛の偉大さを自ら示されました。これは華々しいイベントでも大げさなパフォーマンスでもなく、身近で目に見える低い姿での献身、弟子たちの足を洗われるような仕えの態度を通じて明らかにされました。
ヨハネの福音書13章で、イエス様が弟子たちの足を洗われる場面は、十字架への道が始まる象徴的な出来事です。その箇所では、「世にいる自分のものを愛して、彼らを最後まで愛された」と記録されています(ヨハネ13:1)。「最後まで」という言葉には、私たちの裏切りや拒絶、忘恩にもかかわらず、限りなく忍耐し包み込む神の思いが込められています。この十字架の愛は、単に私たちに倫理的教訓や慰めを与えることを目的としたのではなく、実際に救いと回復をもたらす出来事でした。人間が罪のゆえに永遠の死へ向かっていた時、主はご自身のいのちを差し出し、私たちにいのちを与えてくださったのです。私たちが「イエス様を愛する」と告白するとき、その背後には「主がまず私を愛してくださった」という歴史的事実が置かれています。
では、なぜこれほど偉大で犠牲的な愛の物語が「福音」と呼ばれるのでしょうか。福音とは、ただ神の存在を知らせるだけの情報ではなく、「神が私たちをこのように愛してくださった」という宣言であり、その愛によって人は罪から救われ、真のいのちを得ることができるという約束です。ローマ人への手紙5章でパウロは、「私たちがまだ罪人であったときにキリストが私たちのために死なれたことによって、神はご自分の愛を明らかにされた」と語ります。つまり救いは、私たち自身の努力によって得る業績ではなく、徹底的に神の恵みであり、その恵みは神が先に愛を施してくださった事実によって示されます。私たちはその愛に気づき、それに応答して感謝と献身の生涯を歩むようになります。それが福音が生活の中で実現していくプロセスです。
聖書が語る愛は、単に「愛している」と言うだけのスローガンではなく、具体的に「仕え」と「犠牲」として現れます。イエス様が徴税人や罪人たちと食卓を囲まれた時、パリサイ人や律法学者たちは非難しましたが、イエス様は意に介されませんでした。むしろ、彼らのもとへ自ら出向き、共にとどまり、彼らの罪を責めつつも同時に赦しと回復を与えてくださいました。真の愛とは、そのように「自分で足を運んで近づいていく愛」です。
もし私たちがイエス様を真に知ったなら、同じ愛をもって人々に仕え、受け入れることができるはずです。イエス様のように、罪人や徴税人、そして私たちの人生において最も疎外され苦しむ人々を顧みるとき、私たちはキリストの愛を最も具体的に示すことになります。張ダビデ牧師が繰り返し説いてきたように、教会が社会で「光と塩」の役割を果たすためには、まさにこのイエス様の犠牲的愛を土台として、日常生活の中で助けを必要とする人々を積極的に探し出していく姿勢が非常に重要です。言葉だけで福音を伝えるのではなく、行動で福音を示す時、人々は福音の真の意味を目の当たりにし、心から悟るようになるのです。
私たちは皆、心の奥底に「牧者の心」を持っていることを自覚すべきです。なぜなら、神が人間を「ご自分のかたち」に創造されたので、私たちの内には、困っている人を見て憐れむ感情や、弱いいのちを守ろうとする本性が備わっているからです。世の常識は、多くの場合「99という多数を優先する」論理です。「1より99の方が大切だ」というこの世の計算に慣れてしまうと、弱者や疎外された人を顧みるために自分の心や時間、資源を使うのは非効率だと感じるかもしれません。けれども福音の論理は全く逆方向を示します。主は迷い出た1匹の羊を探すために、野原に残した99匹を置いてでも旅立つ牧者の物語をもって、「神にとってその1匹がどれほど大切か」を強調されました。
2. 徴税人と罪人の福音
ルカの福音書15章はまさに、この「一つのいのちに対する神の思い」をよく示す章です。1節には「すべての徴税人と罪人たちが、イエスの話を聞こうとして近寄ってきた」と記され、2節ではパリサイ人と律法学者たちが「この人は罪人たちを受け入れて、彼らといっしょに食事をしている」とつぶやいたとあります。ユダヤ社会で「罪人」という言葉は、宗教的・道徳的基準から大きく外れた人々を指すだけでなく、人々に忌避される存在の総称でもありました。ところがイエス様は、そのような罪人を排斥するどころか、むしろ食卓を共に囲み、交わりを持たれたのです。これは単に社会的タブーを破る行為ではなく、律法に馴染んだ人々の根本的な思考様式を揺るがす出来事でした。
パリサイ人や律法学者は、ユダヤ教社会や宗教界で尊敬され、律法を厳格に守る人々でした。彼らは「聖」と「区別」を強調するあまり、自らを罪人と徹底的に隔絶し、ともに食事すらしませんでした。しかしイエス様はその垣根を取り除き、罪人たちを受け入れ、彼らの人生のただ中に入られたのです。福音とはまさしく、このような「見知らぬ交わり」を通じて実際に伝わっていきます。遠くから「お前たちは罪人だ。すぐ悔い改めよ」と叫ぶのではなく、傍に近づいて手を取り、立ち上がらせてあげる姿こそが、イエス様が示された福音でした。
ルカの福音書15章に登場する迷子の羊、失われた銀貨、そして放蕩息子(帰ってきた息子)のたとえ話は、いずれも同じテーマを含んでいます。一見価値がないように思われ、罪に染まった人々に対する神の執拗な救いの意思と、回復された後にともに喜び合う天の喜びを示しているのです。イエス様はこれらのたとえを語られて、「神の喜びは、義人九十九人よりも、罪人一人が悔い改めることに、いっそう大きく現れる」と宣言されました(ルカ15:7)。これは論理や効率ではなく、愛によって動かれる神の思いなのです。
実際、徴税人や娼婦は当時の律法社会で最も蔑まれた層でした。徴税人は金銭の奴隷となった者として見下され、娼婦は性的な罪で最大限の軽蔑を受けていました。しかしイエス様は「徴税人や娼婦は、あなたがた(パリサイ人)より先に神の国に入るだろう」(マタイ21:31)とさえおっしゃいました。彼らは罪が多い分、赦しを受けた時の感謝と喜びもいっそう溢れ、その感謝こそが最終的に人生の完全な悔い改めと変化へつながったのです。「罪の増し加わったところに恵みもいっそう満ちあふれる」というパウロの言葉(ローマ5:20)のように、大きな罪を悔い改めた人ほど、恵みと感謝を深く味わうという逆説が示されています。
このような愛と救いのメッセージは、現代の私たちにも同様に当てはまります。時に世の風潮は「価値のある人とそうでない人を分けるべき」「投資対効果が高いところに資源を集中すべき」と語ります。教会でさえ、このような世俗の論理を受け入れ、より「有能そう」に見える人、より「多く持っている」人を歓迎し、それ以外の人を放置または軽視してしまうことがあります。しかし福音の本質は、まったく別の方向を指し示しています。迷える一匹の羊を探すためにいとわぬ労を払い続ける、あの牧者の心こそがイエス様が語られる教会の本質であり、その愛こそ、失われた魂を救い出す原動力となるのです。
イエス様はこの「低いところへの関心」を何度も強調されました。マタイの福音書25章、オリーブ山での説教の最後の部分では、「最も小さい者にしたことは、すなわち私にしたのだ」と語られています。これは、主が私たちに望んでおられるのは「貧しく疎外された者への具体的な関心と愛」であるということをはっきり示しています。その愛を実践することこそ教会の責務であり、その道を通して私たちはキリストの御国をこの世に広げていくことができます。張ダビデ牧師は、宣教のさまざまなアプローチにおいて、「福音は言葉だけでなく、具体的な行い(deed)を伴わなければならない」と繰り返し強調してきました。言葉と生き方が一致しない福音は半分にすぎず、人々の心を動かすことはできないというのです。
したがって教会がこの福音の働きを拡大していく際、まず持つべき姿勢は、「世で最も弱く疎外された人々を探し、彼らに近づくこと」です。ルカの福音書15章4節の「あなたがたのうちに、羊を百匹持っている人がいて、そのうちの一匹を失ったら、その失った羊を見つけるまで探し回らないだろうか」というみことばは、イエス様が私たち全員に本来備わっている「牧者の心」を呼び覚ましておられます。パリサイ人や律法学者たちはその心を失っていたため、徴税人や罪人を見下し、彼らと食卓を共にするイエス様を非難しました。しかし本当は、私たちの内面の深いところに、迷える一匹の羊を思って胸を痛める想いがあるのです。問題は、世の価値観や忙しい日常、あるいは自分の利己心がその思いを抑え込んでしまうことにあります。
主は私たちに、そのような障壁を乗り越えるよう望んでおられます。教会が大きくなり、さまざまなプログラムが増え、財政的資源が豊かになるほど、いつしか「失われた一匹」よりも「既に集まっている九十九匹」のために、便利で効率的な働きを選びがちです。しかし福音は一人の魂を大切にするよう教えます。そしてその一人の魂が悔い改めて帰ってくるとき、天では大いなる喜びの宴が開かれることを思い出させます。
ルカの福音書15章5節、6節を見ると、「見つけたら大喜びでその羊を肩に担いで、家に帰って友達や近所の人々を呼び寄せ、『いっしょに喜んでください。なくした羊を見つけましたから』と言う」と記されています。失われた羊を探しに行った牧者は、その羊を見つけたときに最高の歓びを味わいます。それは物を一つ見つけた安堵感とは次元を異にする喜びです。いのちを生かし、関係を回復させることによる喜びは、この世のいかなる喜びとも比べられない真の歓びなのです。
それゆえに私たちが本当に神を喜ばせたいのなら、失われた魂への関心を決して失ってはなりません。神が最も喜ばれるのは、罪人の一人が悔い改める瞬間です。ルカの福音書15章7節のみことば「悔い改めを必要としない九十九人の義人よりも、罪人がひとり悔い改めることのほうが、天にはもっと大きな喜びがある」はそれをはっきりと示しています。
ここで忘れてはならないのは、「悔い改め」が単なる道徳的反省や形式的な罪の告白を意味するのではないということです。聖書的な悔い改めは「方向転換」です。人生の目標や価値を根本から変えてしまうことであり、そこには、自分が罪を認め、神の赦しを信じ、二度とその罪の道へ戻らないという意志が含まれます。真の悔い改めは、神の愛を深く悟れば悟るほど可能になります。なぜなら、神の愛がどれほど大きいかを知る人ほど、罪の深刻さや自分がその罪からどれほど大きな恵みを受けたのかを強く実感できるからです。その恵みを大きく悟る人ほど、感謝と献身が自然に生まれ、その人は福音の力を証しする通路となります。
ペテロを例に取ることができます。イエス様はペテロがやがてイエスを三度否認することをすでにご存知でしたが、「しかし、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい」(ルカ22:32)とおっしゃいました。ペテロが罪を犯すことになるが、その罪から立ち直り真に悔い改める過程を通して、より大きな愛の証人となるだろうという意味でした。これは私たちにとっても大きな慰めと挑戦です。私たちが罪によって倒れても、その場で悔い改めて方向転換をするならば、神はその弱さすらも用いて、さらに大いなる恵みと愛を分かち合う器としてくださるのです。これこそ律法の世界とは違う、福音の世界です。律法の世界では「罪を犯したなら罰を受ける」のが当然の秩序ですが、福音の世界では「赦しによって変化が起こる」という神の信頼が優先されるのです。
張ダビデ牧師は、数多くの説教や講演の中で「徴税人と罪人を受け入れたイエス様の生涯こそ、教会の永遠のモデルだ」と教えてきました。彼の教えによれば、教会がキリストのからだとして存在するためには、世の人々に対して閉ざされた家ではなく、常に開かれていて、新たなチャンスを提示し、一人でも多くが悔い改めて戻ってこられるよう門を大きく開けておかねばならないといいます。また、今日の教会はもっと積極的に、社会の影に隠れた場所、貧しく病んでいる人々、ホームレス、外国人労働者、脱北者、移民など、この世で最も低いところにいる人々を訪ねて奉仕し仕える働きを通して、イエス様の福音を実際に示すべきだと強く主張しています。これこそ「徴税人と罪人の福音」の精神を受け継ぐ教会の使命だというわけです。
今日、教会が大型化し、多くの財政や資源を手にするようになる中で、社会から「成功」を認められることも悪いことではありません。しかし、そのような物質的豊かさは、しばしば私たちの視野を狭め、貧しい者や弱い隣人を見過ごす誘惑をもたらします。イエス様が語られた「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」(マタイ22:39)という戒めは、頭の中に留まる観念だけではなく、ルカの福音書10章の善きサマリア人のたとえのように、現実に「血まみれで倒れている隣人」を見捨てず、実際に助ける愛の実践にほかなりません。それこそが福音であり、教会がこの地上で担うべき役割です。
この使命のためには、時に組織的な努力とともに個人の献身が求められます。ある教会は宣教地に直接学校を建て、医療宣教や教育の働きを広げながら、現地の人々の生活を改善しようと努力しています。張ダビデ牧師は「来年の教会設立30周年を迎えるにあたって、貧しい国々に300の学校を建てよう」というビジョンを示し、その目的は単なる「建物を建てること」ではなく、失われた魂を探し出し、彼らに福音の実際的な恵みをもたらすことだと力説してきました。学校を通して子どもたちが教育を受け、病気から解放され、自らの将来を描く機会を得るならば、それはただの宣教プロジェクトを超えて、「失われた羊を探しに行く福音」の実践そのものとなるのです。
このように福音は、私たちに「新しい目」を開かせます。かつては気にも留めなかった人々を新たに見つめ、その人たちと喜びや悲しみを共有し、必要を満たそうとすることに喜びを感じるようになるのです。それは世の計算論では到底理解できない逆説的な世界です。一匹のために九十九匹を後に残していく世界、貧しい者や病んだ者にまず手を差し伸べる世界、罪人を頭ごなしに断罪するのではなく、悔い改めて戻る道を開いてあげる世界、これこそ私たちが言う神の国です。
私たちはイエス様のみことば、「あなたがたのうちに羊が百匹いて、そのうちの一匹を失ったなら、残りの九十九匹を野原に残してでも、その失われた羊を見つけ出すまで探し回らないでしょう?」(ルカ15:4)を日々黙想すべきです。そして私たちの日常生活の中で、本当に失われた羊たちを探しているのか、彼らのために時間と心を費やしているのかを振り返らなければなりません。教会の中でも同様です。初めて教会に来た新来者や、過去の失敗や傷のために心を閉ざしている人を見過ごしていないか、自問する必要があります。福音とは、まさにそういった人たちに最初に手を差し伸べるようにと促すイエス様の声だからです。
「徴税人と罪人の福音」とは、単に犯罪者や特定の重い罪を犯した人のためのメッセージではなく、「すべての人間が神の前では罪人である」という聖書の教えに基づく概念です。私たち皆が神の前では罪人であり、恵みを必要としている存在なのです。イエス様は「わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためだ」(ルカ5:32)と宣言されました。これは「自分は正しい人だ」と思い込むことで、「この言葉はあの人だけに当てはまるのだ」と勘違いしないようにという警告でもあります。実際、私たち一人ひとりがイエス様の救いの計画に含まれる「失われた羊」でしたし、主はまさに私たちを探し出し「最後まで」愛してくださったのです。
張ダビデ牧師が投げかける「私たちは本当に、失われた羊一匹を想う牧者の心を持っているのだろうか?」という問いは、教会がこれからも問い続けるべき本質的な問いです。教会の建物やプログラムを増やしたり、信徒数や献金を増やすことも大切かもしれませんが、もっと根源的で本質的な働きは「低いところにいる人々を探しに行き、彼らと共に泣き、共に笑いながら、福音を具体的に伝えていくこと」だからです。私たちはしばしば「自分にはそんな力はない」と言いたくなりますが、使徒の働き3章でペテロが語ったように、「金銀はわたしにはない。しかしわたしにあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストのみ名によって(歩きなさい)」という確信と勇気を持つ必要があります。福音それ自体が最も大きな賜物であり、力だからです。
神は失われた羊を探すとき、その愛の労苦を天で大いに喜ばれます。そしてその喜びに私たちも共にあずかることができます。ルカの福音書15章で、失った羊を見つけた牧者は友だちや近所の人を呼び集め、「いっしょに喜んでください。迷子の羊を見つけたのです」と叫びます。教会とはまさに、この喜びを人々と共有する共同体です。すなわち救いの喜び、悔い改めの喜び、赦しの喜びを互いに分かち合い、神の国の宴をあらかじめ味わわせる役割を担っているのです。
結論として、福音は「徴税人と罪人の福音」です。イエス様が示された生き方と教えは、失われた者を狙い撃ちにする具体的な献身と愛でまとめられます。徴税人や娼婦が悔い改めて神の国に入り、大きな罪を犯した人が赦されて一層大きな感謝をもって神に仕えるようになる――そうした世界こそ、イエス様の福音がもたらす革命的な変化です。私たちはこの愛を単に頭で理解するだけでなく、実際の生活の中で実践することで証ししなければなりません。張ダビデ牧師が強調してきたように、「世の弱者や疎外された隣人に、私たちが受けた恵みを分かち合う」という呼びかけは、福音の最も根本的な叫びなのです。そしてそれは決して大げさだったり不可能な要求ではなく、すでに私たちの内に潜んでいる「牧者の心」を呼び覚まし、イエス様の足跡をたどれば自然に流れ出る使命です。
今日もこの世界には、私たちが見過ごし、通り過ぎてしまう多くの「失われた羊たち」が苦しんでいます。もし教会が真の福音共同体であるならば、彼らを探し回り、世話をするはずです。金銭の奴隷となった徴税人も、愛に破れた娼婦も、人生にさまよっている若者も、病床で苦しむ人も、自死を考えるほど追いつめられた魂も、みな神の子どもとなる道が開かれており、教会はその道へ導く牧者の心を持たねばなりません。「徴税人と罪人の福音」が現代の私たちの教会と信徒の生活を通してもう一度力強く宣言され、キリストの愛が実際の感動と変化へとつながるならば、天には言葉に尽くせない喜びが満ち溢れるでしょう。それこそが、「悔い改めを必要としない九十九人の義人よりも、罪人が一人でも悔い改めることを喜ばれる」(ルカ15:7)という主のみ声を、この地上で体験する道なのです。そしてその体験こそ、福音の核心が「愛」であることを最も生き生きと証明することになるでしょう。
張ダビデ牧師は、この「徴税人と罪人の福音」を韓国の教会だけでなく世界の教会が改めて深く悟り、福音の力が私たちの社会や宣教地のあちこちで具体的な人生の変化をもたらすよう、切に願っています。都会や農村、貧しい国や豊かな国を問わず、教会が「失われた羊を探す牧者の心」に立ち返るならば、数えきれない魂が回復し、神の御名は大いに崇められるでしょう。私たちがこの愛の召しに応えるとき、福音は生き方によって証しされ、その証しがさらに広がって多くの罪人が悔い改め、赦しと癒し、回復を経験するようになります。この全過程の中で、教会は世界に真の希望をもたらし、神の国が「今ここで」すでに広がっているという事実を明確に示すことができるのです。こうして福音は絶え間なく拡大し、多くの人々がイエス・キリストの愛を目撃し、共に救いの宴を享受できるようになるでしょう。
このように福音は、単に聞くだけの教えではなく、徴税人や罪人までも受け入れ、共に食事をされるイエス様の生き方そのものです。主が先に私たちを愛してくださったからこそ、私たちもその愛を知り、伝えることができるのです。ゆえに、失われた羊一匹を探しに行くその歩みこそが、教会が本来担うべき使命の核心であり、「徴税人と罪人の福音」がこの世で完全に具現されるための通路なのです。そしてその道を歩むすべての献身者、牧会者、信徒たちには、神が「よくやった、忠実な僕よ」と称賛を用意してくださっていると、私たちは信仰によって告白します。そのために今日も絶えず祈り、実際に歩み出す教会と信徒でありたいと願うものです。